高配当ETF QYLD
最近になって人気が高まってきているのが、GlobaLX社が販売しているカバードコール戦略を取っているETFです。GlobaLX社は大和証券グループと大和アセットマネジメントの合弁会社で日本で唯一のETF専門資産運用会社として金融商品を展開しています。
・QYLD(Nasdaq10)
・XYLD(S&P500)
この2つがGlobaLX社の主力商品です。QYLDはNasdaq100、XYLDはS&P500をベンチマークとしています。
・純資産総額 60億ドル
・基準価格 16.46ドル
・経費率 0.6%
・分配利回り 12.05%
・毎月分配
QYLDのデータを確認すると、2022年9月19日時点ではこのようになっています。人気の理由は分配利回りが非常に高いことですね。
・Nasdaq100をベンチマークとしながら、年間10%以上の分配金を出す
・下落局面でも分配金が出る
これがカバードコール戦略を取っているQYLDの人気の理由です。しかし、カバードコール戦略は仕組みがやや複雑です。
・カバードコール戦略とは
・QYLDは投資対象として適切か
・QYLDはどのような投資家に向いているか
今回はこの3点について考えてみたいと思います。
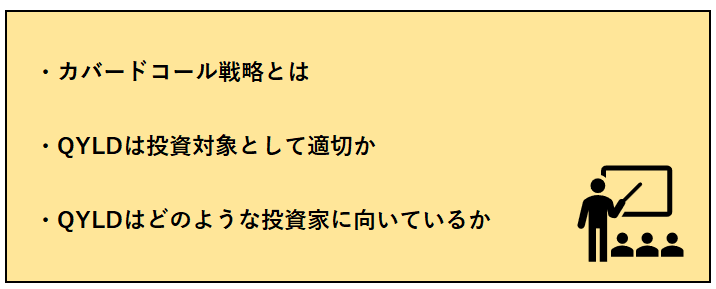
カバードコール戦略
カバードコール戦略とは、株式などを保有しつつ、コールオプションを売る戦略です。保有する原資産については、権利行使価格以上の値上がりを放棄する対価としてオプションプレミアムを受け取ることができます。
通常のETFの場合、企業の配当金からランニングコストが引かれたものが投資者に分配される仕組みです。
しかし、カバードコール戦略を取っているETFは特定の銘柄を買う権利を売って、利益を上げる仕組みを取っているというこです。利益を先取りしているといのがしっくりくる表現です。
・指数が下がった時にも利益を出すことができる
・指数が暴騰した時はそれほど利益を上げることができない
カバードコール戦略で抑えておきたいポイントはこの2点です。一番の特徴は指数が下がった時でも利益を出せるということです。これはコールオプションによって、利益の先取をしているからですね。

カバードコール戦略は投資対象として適切か
カバードコール戦略が投資対象として適切かどうか、例を出して考えてみます。
・Nasdaq100 → りんご
・QYLD → 農家
このようにしてカバードコール戦略を考えてみます。
りんごが100円で売られていた場合、特定の日(4/1とします)に120円で買うことができる権利を農家が売って、得た利益をオプションプレミアムといいます。この場合は20円ですね。
・120円(買う権利)-100円(現在のりんごの価格)=20円(オプションプレミアム)
農家はりんごが4/1時点で120円を超えても値上がりは放棄しなければなりません。仮に、りんごが90円になった場合、りんごを120円で買うことができる権利を売っているので、値下がり分の10円をオプションプレミアムの20円で補填することができます。実質的な利益は10円です。
・90円(値下がりしたりんご)-100円(以前のりんごの価格)=-10円
・20円(オプションプレミアム)-10円(りんご売買の損益)=10円(農家の利益)
そして、りんごが150円になった場合、120円までの値上がり益20円とオプションプレミアム20円を得ることができます。この場合の実質的な利益は40円となります。
・120円(150円までの値上がりは放棄)-100円(以前のりんごの価格)=20円(りんごの値上がり益)
・20円(オプションプレミアム)+20円(りんごの値上がり益)=40円(農家の利益)
【りんごの値段が下がった場合】
・値下がり損失 -10円
・オプションプレミアム +20円
・計 +10円
※カバードコール戦略を取っていない場合は、りんごが100円から90円になっているので、-10円となる
【りんごの値段が上がった場合】
・値上がり益 +20円
・オプションプレミアム +20円
・計 +40円
ここまでを表にしてみると以下のようになります。

本来は値段が下がっている時は損失が出るのが一般的ですが、それをオプションプレミアムでカバーしているということです。しかし、オプションプレミアムを上回るような値段の上昇があれば、利益を取り逃がしてしまう仕組みです。

一方で、普通に売買した場合は、このように値段の上下によって利益と損失が出るようになっています。QQQなどはこの仕組みで利益を出しているということです。
ここからわかるとおり、カバードコール戦略は下落局面に強く、安定した配当が見込めるということです。逆に、上昇局面では、利益を放棄してしまうことになるのです。
このような仕組みを考えると、カバードコール戦略を取っているETFは真っ当な仕組みをしています。
・タコ足配当の毎月分配型の金融商品
・仕組みだけが複雑で手数料が割高
カバードコール戦略を取っているETFはこのような金融商品ではなく、投資対象としては考える余地がある金融商品だということです。
QYLDはどのような投資家に向いているか
QYLDのようなカバードコール戦略を取っているETFは万人にオススメできる金融商品かと言えばそうではありません。ずばり言ってしまえば、投資対象とすることができる投資家というのは限られています。
カバードコール戦略の最大のメリットは下落局面でも利益を上げることができるということです。
・VOO
・QQQ
このようなETFの場合、構成銘柄の株価が下落すると等しく価値も下落しますが、同様の指数をベンチマークとしているQYLDやXYLDはコールオプションによって、利益を出すことができるということです。
しかし、上昇局面ではVOOやQQQと比較すると暴騰率が低くなってしまうということですね。
このことから、どちらかと言えば、ディフェンシブに使うことができるETFという印象です。急激な値上がりを期待するような、サテライト的に保有するようなETFではないですね。
・定年退職して年金の足しに毎月お金が欲しい
・指数の下落を予想しているが、インバース系ETFを購入するほどではない
このような投資家とは相性がよいETFだということです。そして、資産形成段階の投資家には向かないETFだと私は考えています。

QYLD 銘柄 - Global X Nasdaq 100 Covered 投資信託(ファンド)情報 - Bloomberg Markets
オレンジ色がQYLD、青色がVOOの直近1年のチャートです。両方とも同じ動きをしていますが、値上がり幅が大きく違っていることがわかります。
これは、QYLDのようなカバードコール戦略を取っているETFは値上がり益を再投資せずにそのまま分配金としているからですね。
そのため、分配金を受け取ることはできるが、QYLD自体の価値は増加していかないということです。

YOHの考え
カバードコール戦略を取っているETFの最も大きな特徴は分配金の多さです。
・毎月分配
・10%以上の高利回り
このような特徴がQYLDの人気の理由です。ベンチマークをNasdaq100としていることからの安心感もありますね。しかし、カバードコール戦略を取っているETFの最大の強みは下落局面でも利益を出すことができることだと、私は考えています。

一般的な投資手法であれば、損失を出すような場面でもコールオプションによって利益の先取をしていることによって、損失を回避できることが大きなメリットだということです。
しかし、誰にでもおすすめできるETFであるかと言えばそうではないですね。
・ETF自体の成長性は無い
・複雑な仕組みのため、経費率が高め
・分配金を受け取る度に税金がかかるため、資産増加効率が悪い
このようなデメリットがあるからです。私自身は、現時点ではカバードコール戦略を取っているETFに資産投下することは考えていませんが、非常に面白いETFだと考えています。
・資産を増やす状況を終えている
・安定した分配金が欲しい
このような方は資産投下を考慮してもよいということです。複雑な仕組みを取っている以上、経費率はそれほど下がることはないでしょうが、純資産額から見ても、一定の評価を得ていることは明らかです。
しかし、資産形成段階の投資家でそこまで複雑なETFを購入する必要があるかということは、個人で考える必要があるということです。ご覧いただきありがとうございました。
誰にでもおすすめできるのは、SBI・Vシリーズなどですね。資産増加させる面においてこれほど優れた投資信託は見当たりません。
サテライト的に持つのは新興国株式などが向いています。その分ボラティリティは大きくなりますね。
他には不動産ETFもサテライトの候補に挙がります。不動産は資産規模が大きくなればポートフォリオに入れることを考えてもよいですね。



