【有給休暇引当金】有給休暇を取らないことは年収を下げていることと同じ
有給休暇を習得できない
日本では年次有給休暇は労働基準法によって、労働者に与えられた権利とされています。
しかし、全ての年次有給休暇を全て使うことができる労働者というのは多くは無いですね。
よほど労働環境が整っている企業で働いていなければ、年間数日取得して、あとは消化することができないというのが一般的な感覚です。
・有給休暇を取らないことを前提とした人員配置がされている
・職場の雰囲気によって取りにくい
年次有給休暇を取得できない理由としては、このようなことが主な原因ですね。
平成31年4月に労働基準法が改正されて、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、年間5日以上の年次有給休暇の消化が必要となりましたが、それでも、最低限の消化に留まっている労働者は少なくないということです。
・冠婚葬祭の時にしか消化できない
・特段の用事がなければ申請することがためらわれる
このような労働環境は今もそれほど変わっていないということです。
しかし、年次有給休暇は資産形成の面から見ても、できるだけ消化した方がよいですね。年次有給休暇を習得しないということは、自分の給料や年収を下げていることと同じことだからです。
・年次有給休暇について
・有給休暇引当金について
今回はこの2点について考えてみたいと思います。
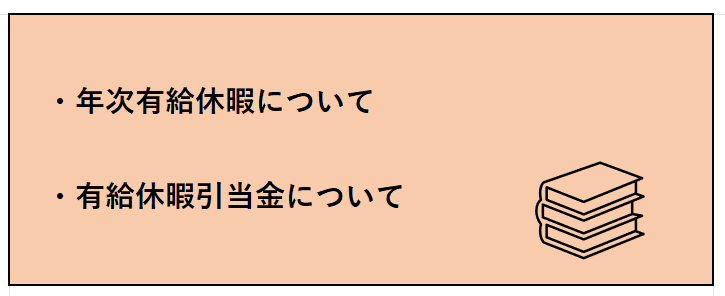
年次有給休暇
年次有給休暇とは、一定期間勤務している労働者に対して、ゆとりある生活を保護するために与えられる休暇で、習得しても給料が減額されない休暇です。
年次有給休暇は労働基準法によって全ての労働者によって与えられた権利で、一定の労働条件を満たした労働者全てに認められています。
・半年間継続して雇用されている
・全労働日の80%以上勤務している
この2つの条件を満たしていれば、パートタイムジョブで働いている方にも付与されます。
付与日数は勤続年数が6年6カ月以上であれば年間20日付与されることになっています。

パートタイムジョブの方であれば、労働条件や継続勤務年数によって差がありますが、同じところで5年以上週3日働いていれば、年間8日は取得する権利があります。

しかし、付与されて習得する権利があると言っても、全てを取得することができるわけではないですね。
・職場の人員が慢性的に不足している
・勤務形態が年次有給休暇を習得することを前提に構成されていない
このような労働条件である職場が多く、労働者の大半が付与された日数を消化できていないというのが実情です。
しかし、年次有給休暇を消化しないということは、自分の労働力を職場にプレゼントしているということと同じです。
職場側から見れば、消化されていない年次有給休暇は負債であるということです。そのような負債は有給休暇引当金と言われています。
有給休暇引当金
有給休暇引当金とは、会計上で言えば、負債性引当金の一種です。
負債性引当金とは、将来の支出に備える引当金のことで、簡単に言えば、将来予想される支出を前もって計上しておくお金のことです。
・賞与引当金
・退職給付引当金
・修繕引当金
負債性引当金を例に挙げるとこのようなものが該当します。そして、有給休暇引当金もこのようなものと同一だということです。
・年次有給休暇の日数
・今までの平均取得率
・日給
有給休暇引当金はこの3つを掛け合わしたもので求めることができます。
・年次有給休暇日数 20日
・今までの平均取得率 60%(12日)
・日給 1万円
このような職員の場合、有給休暇引当金は12万円となります。
実際の計算方法は非常に複雑で、平均取得率は繰り越しなどを考慮する必要があります。そして、日給に関しては給料だけではなく、社会保険料の会社負担分や福利厚生なども加味されます。
そして、この職員が今年に年次有給休暇を5日しか取らなかったのであれば、有給休暇引当金の内、7万円を回収することができず、職場にプレゼントしていることになるということです。
この有給休暇引当金は日本の会計上は処理されることはなく、米国などの会計基準で用いれらて使用されています。

YOHの考え
今回は年次有給休暇と有給休暇引当金について考えてみました。
有給休暇引当金という考え方は日本では考えられないような、いかにも米国やヨーロッパ諸国らしい考え方だと感じますね。
日本では労働環境の見直しが行われているひと昔前よりは年次有給休暇の取得はしやすくなっていると感じますが、付与されるに日数全てを消化できている労働者というのは多くはないですね。
私の職場でも、以前と比較すると格段に消化しやすくなっていますが、それでも全員が全ての日数を消化できる環境ではないですね。
・人員不足
・労働力不足
このようなことに日々向き合いながら仕事をこなしているのが実情です。
特に、いまだに縦社会制度が色濃く残っているような職場では、ベテランと言われる方を中心に有給休暇をよしとしない雰囲気があります。
・昔は有給休暇は冠婚葬祭の時だけ
・有給休暇を取ることは仕事をさぼっている
このように考える職員が一定数いるということです。
しかし、今は時代が変わっているということです。
・給料が右肩上がりに上がることはない
・社会保険料、税負担が増加し使えるお金が減っている
・退職金や年金などの老後資金はあてにできない
このようなことからを考えると、有給休暇ぐらいは取らして欲しい、というのが多くの労働者の願いであるということです。
もちろん、無理に全ての年次有給休暇を取得することは不可能ではありません。
・労働基準法を振りかざす
・与えられている権利全てを主張する
このようなことをすれば、毎年全ての年次有給休暇を取得していくことはできると感じます。
しかし、無理に権利ばかりを主張していては、その分のしわ寄せが誰かにいってしまうのですね。
もちろん、このような労働環境は職場側が是正する必要があるのでしょうが、それでは職場が回らないというのが現実問題としてあるということです。
私の職場では、年次有給休暇を取得していない職員は頑張っているという考えを持つ方が一定数おられます。
・出世したいのであれば、年次有給休暇は最低限にした方がよい
・用事の無い年次有給休暇の取得は良くない
このような価値観があるということです。しかし、年次有給休暇を全く取得しないというのとはお金の面から考えてもよいこととは言えないですね。
それは、有給休暇引当金の考え方からも明らかで、有給休暇を取得しないということは、職場に対して無償で労働力を提供しているということです。
・休む時はしっかりと休む
・働く時はしっかりと働く
休みと労働に関しては、このようなスタンスで取り組んでいれば大きく批判されることはありません。
給料や年収、労働環境が同じであるなら、休みが多い方がよいのは間違いがありません。
そのような環境を作るためには、周囲に迷惑をかけない範囲でしっかりと年次有給休暇を消化することが大切だと私は考えています。
ご覧いただきありがとうございました。
有給休暇に限らず、会社員や公務員は資産形成上不利であることが多いですね。それを自覚することが資産形成には大切です。
出世を諦めた公務員であっても、年次有給休暇を全て取得することは難しいですね。周囲との兼ね合いが大切です。
権利ばかりを主張してしまうと、老害と言われるような職員になってしまう可能性があります。



